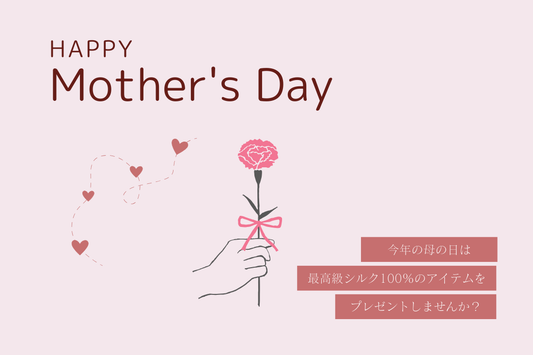接触冷感とは?熱中症対策に役立つひんやり涼しい天然繊維をご紹介

近年では夏の気温も上昇し、ひんやり涼しいグッズが必要不可欠な存在になりつつあります。触れると冷たい接触冷感素材も増えていますが、その仕組みを理解している人は案外少ないかもしれません。
そこで今回は、接触冷感の仕組みをはじめ、接触冷感素材の選び方や接触冷感機能を備えた天然素材など、接触冷感素材の全貌を明らかにしてまいります。
目次
接触冷感とは?

そもそも接触冷感とは「肌に触れた瞬間にひんやり冷たく感じる効果」のことで、この効果をもつ生地を接触冷感素材と呼んでいます。夏場の日陰で鉄やコンクリートに触れた時、ひんやり感じたことはありませんか?このような現象が接触冷感にあたります。
接触冷感の仕組み
物を触ってひんやり感じた時は、肌と物の間で熱の移動が起きています。実は熱には高温から低温へ移動する性質があり、皮膚より冷たい物に触れると体温が奪われて冷たく感じるのです。これを熱の伝導性といい、熱の伝わりやすさをわかりやすく数値化したものを「熱伝導率」といいます。
接触冷感素材では接触した部分の体温が生地に奪われて、ひんやり冷たく感じられる仕組みです。ちなみに、熱伝導率が高いものほど冷たく感じられると言われています。
接触冷感素材の特徴

接触冷感素材の最大の特徴は熱伝導率が高いこと、すなわち熱が移動しやすいということです。熱伝導率の高い素材は肌から体温を奪って、冷たさや涼しさを感じさせます。
また、接触冷感素材には様々な質感があり、多くはサラッとした肌触りで、汗によるベタつきやまとわりつきを抑えてくれます。シャリっとした清涼感のある風合いも、接触冷感素材に見られる特徴の一つです。生地にはハリがあって肌にまとわりつきませんが、やや硬さがあります。
接触冷感の指標となるQ-max値
接触冷感素材にどれくらいの効果があるか知りたい時は、「Q-max値」という単位を参考にします。Q-max値(最大熱吸収速度)とは、触れた時のひんやり感を示した値です。単位には「W/㎠」「W/㎥sec」「J/㎠sec」などがありますが、JISで採用されているのは「W/㎠」になります。このQ-max値が0.100以上あれば、接触冷感の効果を有するとされています。
なお、Q-max値が高ければ高いほど冷感効果も高いと言われていますが、他の製品と冷たさを比較する場合は少し注意が必要です。たとえば、一般財団法人カケンテストセンターの測定試験では、試験条件として室温を+10℃(ΔT=10℃)と+20℃(ΔT=20℃)の二つから選ぶことができます。この場合、ΔT=20℃で測定した方がQ-max値は高くなってしまうため、同じ条件で計算し直さない限り、正確な比較ができないのです。したがって、Q-max値を見る時はΔTがそろっているかも着目したいポイントになります。
接触冷感のメリット・デメリット
接触冷感素材は蒸し暑い季節に重宝しますが、実はデメリットがないわけでもありません。接触冷感素材を購入する際はメリットもデメリットも知ったうえで、最良の素材を選びましょう。
【接触冷感のメリット】
ひんやり涼しい

接触冷感素材に触れると肌の熱が奪われて、ひんやりした感覚を得られます。暑い日も接触冷感の衣類を着れば涼しいと感じられますし、心地よさが違ってきます。
また、接触冷感の寝具を使うと快適な睡眠環境が整って、寝つきが良くなります。心地よい入眠をサポートしてくれるので、寝つきが悪い人にとっても重宝するでしょう。
電気代の節約になる
接触冷感素材の衣類や寝具を取り入れると体感温度が変わり、エアコンの温度を少し上げても暑さを感じにくくなります。エアコンの電力消費量は1度上げるだけで10%の節約になるので、電気代の節約につながるというメリットもあります。
冷え予防になる

エアコンを入れっぱなしの環境で冷風を浴び続けると、体が冷えて体調不良の原因にもなりかねません。接触冷感素材は冷えによる体調不良を気にせず使えますし、氷や保冷剤と違って冷却効果もないので、凍傷のリスクもなく安心です。
【接触冷感のデメリット】
ひんやり感が持続しない
接触冷感素材に触れるとひんやりしますが、冷たさがずっと続くわけではないことも知っておくことが大切です。肌と密着している部分は体温で温まってしまうため、しばらく肌から離しておかないと冷感が元に戻りません。したがって、接触冷感素材だけで暑さを凌ぐのは難しく、熱中症対策として活用する場合はエアコンなどの併用も不可欠です。
吸水性・吸湿性が低い

接触冷感素材のなかには吸水性や吸湿性が低く、汗を吸わない素材が含まれている場合があります。
特に化学繊維は汗をあまり吸わないため、痒みやかぶれなどの肌トラブルを引き起こす可能性もゼロではありません。蒸れやすい寝具は不快感で寝苦しさを覚え、睡眠にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
接触冷感効果が高い天然繊維・化学繊維

ひんやり涼しい接触冷感素材を使ってみたいという方に、ここからは冷感効果を備えた繊維をご紹介してまいります。
【天然繊維】
リネン(麻)
リネンは伝導性に優れた天然繊維で、接触冷感素材によく使用されている繊維です。シャリっとした風合いで清涼感もあり、夏にぴったりの素材と言えるでしょう。吸湿性・放湿性も高く、汗をかいても蒸れにくいという性質も持ち合わせています。ただし、リネンは繊維が硬いため、人によっては若干ゴワゴワ感が気になるかもしれません。
シルク(絹)

シルクもまた、接触冷感効果があると言われている天然素材のひとつです。シルクは吸湿性と放湿性に優れた繊維で汗をかいてもベタつかず、サラッとした着心地が続きます。主成分が人の肌と同じタンパク質で刺激が少なく、肌あたりも滑らかです。
【化学繊維】
レーヨン
レーヨンは化学繊維の一種ですが、熱伝導率が高く、接触冷感に優れた性質をもっています。レーヨンは木材パルプを原料とする再生繊維で、シルクに似た光沢と肌触りが特徴です。生地の滑らかさは本物のシルクに劣るものの、他の化学繊維に比べて通気性や放湿性もあります。
ポリエチレン
ポリエチレンは接触冷感素材のなかでも、抜群の冷感効果を備えた繊維です。原料はプラスチックの一種で、レジ袋やペットボトル容器などに用いられています。寝具などにも使われている素材ですが、吸湿性や吸水性が低く、一般衣類にはほとんど使われていません。
ナイロン
ナイロンは石油を原料とする合成樹脂から作られた化学繊維の一種で、ストッキングやインナー、スポーツウェアなどに使われています。ナイロンにも接触冷感機能が備わっていますが、吸湿性・吸水性はあまり高くありません。
夏にぴったりの接触冷感素材の選び方。おすすめの天然繊維とは?

接触冷感素材のなかには、ポリエチレンやナイロンのように吸水性や吸湿性が低い素材もあります。
たくさん汗をかく夏場は吸水性・吸湿性の低い素材を使用すると、蒸れて嫌なニオイやべたつきの原因になります。汗による蒸れは肌荒れを引き起こす恐れもあるので、夏は吸水性・吸湿性が高い天然繊維の接触冷感素材がおすすめです。
なかでもシルクはなめらかな肌触りで肌への刺激も少なく、肌荒れが気になる人も安心して使用できます。化学繊維の機能性素材と比べたらQ-max値は低いかもしれませんが、シルクにも接触冷感機能があることは証明されています。
【夏の眠りに心地いいシルクアイテム】
シルクのパジャマ

腕を通すとひんやりとした心地よさが伝わるシルクのパジャマ。とくに「半袖タイプ」は、短めで熱がこもりにくく、通気性も抜群。寝苦しい夜も快適にお過ごしいただけます。
シルクの布団カバー

暑い夏の寝具選びに迷ったらシルクの布団カバーがおすすめ。吸湿性と放湿性に優れたシルクは蒸れにくく、夏でもサラッとした心地よさ。ふんわり全身を包みながら、ワンランク上の睡眠へと導きます。
シルクのボックスシーツ

ふっくら厚みのある25匁のシルクを贅沢に使用したシーツ。寝汗をかいても蒸れにくいシルク素材は、夏のシーツにぴったりの素材。寝転ぶとひんやり気持ちいい、ツルツルとした肌ざわりが極上の眠りをもたらします。
真夏の熱中症対策にもシルクが大活躍!
接触冷感素材はひんやり涼しいだけでなく、吸水性や吸湿性があることも大事なポイントです。汗による不快感を抑えながら、ひんやり涼しい快適さを提供してくれるシルクをフルに活用して、暑い夏を元気に乗り切りましょう。
ご紹介アイテム
-

レディースパジャマ(半袖) SILK PAJAMAS
最高級シルク100%の半袖パジャマ(上下セット)は夏も涼しくサラサラ。汗で敏感になりがちなお肌にも◎
-

レディースパジャマ(長袖) SILK PAJAMAS
最高級シルク100%の長袖パジャマ(上下セット)。素肌と一体化するような、極上贅沢のなめらかさです。
-

ワンピースパジャマ SILK PAJAMAS
one piece最高級シルク100%のワンピースパジャマ。お肌にやさしく体を締めつけず、どこまでもストレスフリーに。
-

シルク 布団カバー SILK COMFORTER CASE
最高級シルク100%のとろけるような心地よさを、全身で堪能できる布団カバー。至福の睡眠時間をどうぞ。
-

シルク ボックスシーツ SILK FITTED SHEETS
最高級シルク100%を贅沢に使ったボックスシーツ。ずっと触れていたくなる極上質感で熟睡へと導きます。